はじめに
「IT業界に興味はあるけど、“インフラ”って何するのかよくわからない…」
自分自身もそんな状態から、今まさに未経験からIT業界を目指して勉強中です。
中でも「ITインフラエンジニア」という仕事に興味を持ち、自分なりにいろいろと調べてみました。
この記事では、
- ITインフラとはどんな仕事なのか?
- どんな役割や工程があるのか?
- 向いている人や魅力、デメリットは?
ということを、初心者目線でわかりやすくまとめてみました。
これから同じようにチャレンジしてみたい人の参考になれば嬉しいです!
ITインフラとは?社会を支える“デジタルの土台”
“インフラ”とは「インフラストラクチャー(Infrastructure)」の略で、社会を支える基盤のこと。
水道・電気・道路のように、あって当たり前だけど無いと困るものたちです。
それをIT分野に置き換えると、「ITインフラ=ネットやシステムを支える基盤」になります。
例えば:
- Zoomで会議ができるのも、ネットワークが整備されてるから
- アプリがサクサク使えるのも、裏でサーバーが稼働してるから
- クラウドでデータが保存できるのも、ITインフラのおかげ
普段は意識されないけど、全てのITサービスの裏側にインフラがある。
だからこそ、安定した社会やビジネスを支える超重要な仕事なんです。
インフラエンジニアの主な仕事内容
インフラエンジニアの仕事は、ざっくり分けて以下のような流れがあります。
■ 上流工程
- 要件定義:クライアントや社内の「こんなシステムがほしい」というニーズをヒアリング
- 設計:どんなネットワーク構成・サーバー構成にするか、設計書を作成
■ 下流工程
- 構築:設計書に基づいて実際にネットワークやサーバーを構築(設定や配線など)
- 運用・保守:システムが安定して稼働するように管理・対応
- 監視:エラーやトラブルを24時間体制で監視するチームもある
上流工程と下流工程の違い
- 上流工程は、計画や設計など「頭を使う仕事」
→ 技術だけじゃなく、論理的思考力・ヒアリング力・マネジメント力が必要 - 下流工程は、構築や保守など「手を動かす仕事」
→ 実践的なスキルや経験を積むことができる現場
未経験からは、下流工程(監視・運用)からスタートするのが一般的です。
そこで経験を積みながら、上流を目指すキャリアパスが多いです!
向いている人ってどんなタイプ?
自分自身が感じた「向いていそうなタイプ」はこんな人!
- コツコツ作業が苦じゃない
- チームで何かを支えるのが好き
- 目立たなくても、誰かの役に立つことにやりがいを感じる
- トラブル時にも落ち着いて対処できる
私はもともと看護師として働いていて、緊急時の対応や冷静な判断が求められる職場にいました。
一見まったく違う分野のように見えるけど、「人を支える」という点では共通点があると感じています。
調べてわかったインフラエンジニアの魅力、大変さ
インフラエンジニアの魅力
- ITサービスを支える“縁の下の力持ち”になれる
- 将来性が高い分野で、需要が安定している
- 資格やスキルを身につければ、働き方の選択肢が広がる
→ 在宅/副業/フリーランスも視野に入れられる - インフラが止まると社会が止まる=やりがいが大きい
インフラエンジニアの大変な面
- 夜勤やシフト勤務がある現場も多い(とくに監視)
- 障害発生時は、休日でも対応が必要になることがある
- トラブル時のプレッシャーが大きい場面もある
- 最新技術の変化が速く、学び続ける姿勢が求められる
- 裏方の仕事なので、評価されにくいと感じる場面もある
ただし、これらはどの職業にも言える「リアルな一面」でもあります。
事前に知っておくことで、自分の希望する働き方とすり合わせることができると思いました。
最後に
最後に:初心者なりに調べてみて
最初は「インフラって地味そう…?」という印象でしたが、(インフラエンジニアの方々すみません!)
調べるうちに「めちゃくちゃカッコいい仕事じゃん…!」と感覚が変わりました。
見えないところで人や社会を支えるという点は、医療とも通じる部分があり、
自分のこれまでの経験も無駄にならないんじゃないかと感じています。
これからも、未経験なりにコツコツ知識を積み重ねて、
将来的には副業や在宅ワークもできるスキルとして育てていきたいです。
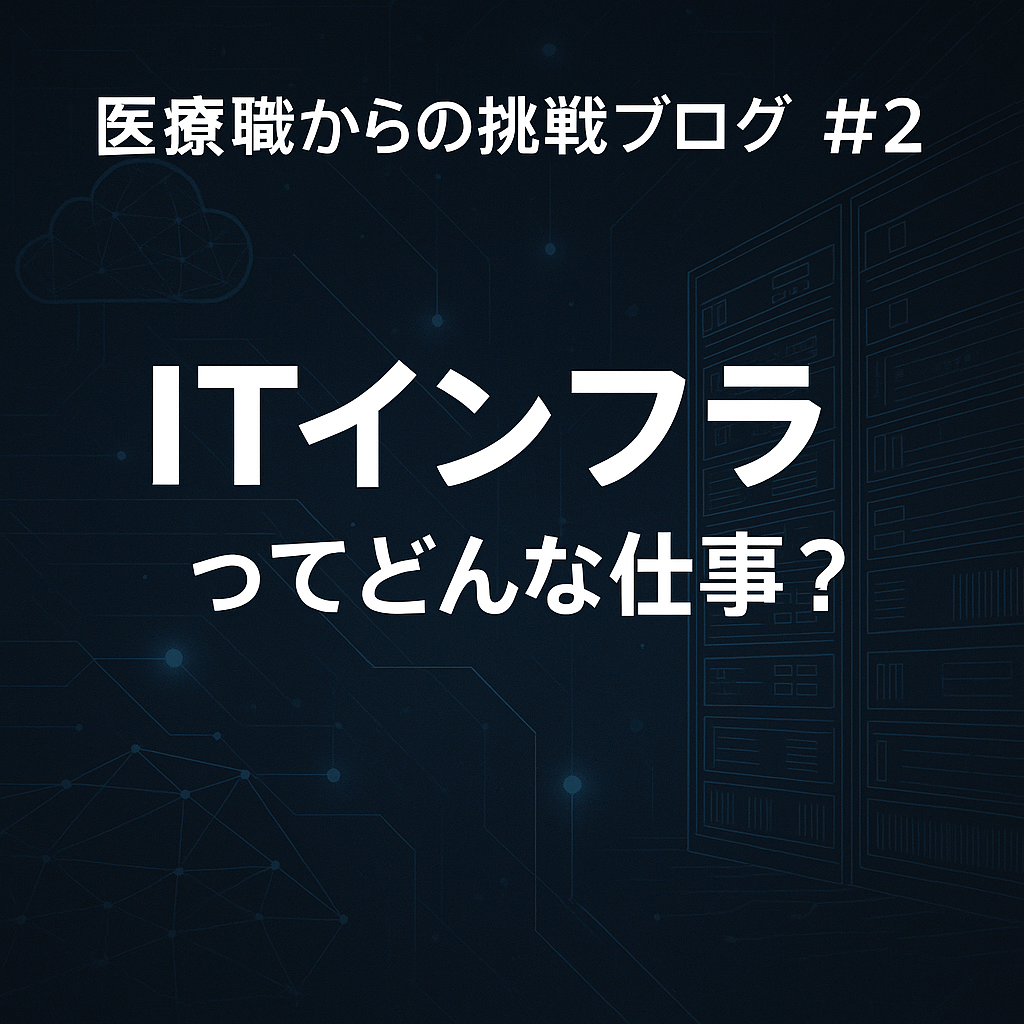
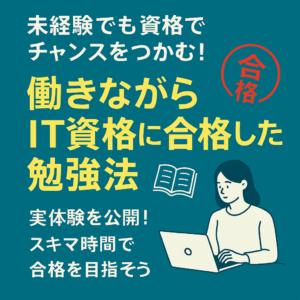

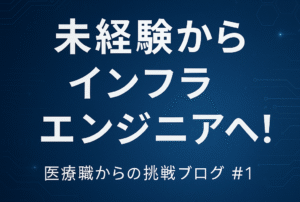
コメント